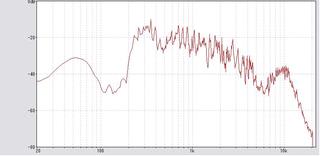「ステレオ再生で、スピーカーはどう置くんですか?」
と聞かれたら、どう答えるか・・・
Phile-webでPolarBearさんの日記を拝読して、
オーディオマニアであり、そしてスピーカーを作っている私なのに、
これほど根本的なことは考えなかったなぁ〜と反省中ですw
さて、私にとってステレオスピーカーの配置は・・・
「左右スピーカーとリスナーの関係は正三角形」
「ツイーターの高さは、耳に近い位置」
「スピーカーは、耳に向けて置く (変な方向は不可w)」
という三条件を基本に、
「上記の『正三角形』はできるだけ大きくする」
「聴感を重視して、自由にスピーカーを動かす」(ずるい条件だなぁ)
という二項目を加えたものです。
この条件なら、デスクトップオーディオでも「0.5mの正三角形」というように適用可能かなぁ〜と思っています。
------------------------------------------------------
では、レコーディング、放送局では明確な定義があるのか??
色々探してみたところ、次のような例がありました。
「Recommendation ITU-R BS.775-2」(Intornational Telecommunication Union 2006年)
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.775-2-200607-I!!PDF-E.pdf
「5.1chサラウンド番組の制作技術ガイドライン」(電波産業会 2010年)
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B30v1_0.pdf
「マルチチャンネルオーディオ用スピーカーセッティングガイド」(パイオニア 2002年)
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=1023
しかし、「ステレオ再生」に関する良い資料はなかなか見つかりません。。。
ようやく見つけたのが、
ダイヤトーンで2S-305やDS10000など、1000機種以上のスピーカー開発に携わった
佐伯多門氏の著書「スピーカー&エンクロージャー百科(誠文堂新光社)」の中にに『ステレオ再生の望ましい配置』として紹介されていた図を見つけました!!
それがコレ。
![]()
<クリックで拡大>
この図をスピーカーカタログに載せたら、売り上げ減少間違い無しですwww
と聞かれたら、どう答えるか・・・
Phile-webでPolarBearさんの日記を拝読して、
オーディオマニアであり、そしてスピーカーを作っている私なのに、
これほど根本的なことは考えなかったなぁ〜と反省中ですw
さて、私にとってステレオスピーカーの配置は・・・
「左右スピーカーとリスナーの関係は正三角形」
「ツイーターの高さは、耳に近い位置」
「スピーカーは、耳に向けて置く (変な方向は不可w)」
という三条件を基本に、
「上記の『正三角形』はできるだけ大きくする」
「聴感を重視して、自由にスピーカーを動かす」(ずるい条件だなぁ)
という二項目を加えたものです。
この条件なら、デスクトップオーディオでも「0.5mの正三角形」というように適用可能かなぁ〜と思っています。
------------------------------------------------------
では、レコーディング、放送局では明確な定義があるのか??
色々探してみたところ、次のような例がありました。
「Recommendation ITU-R BS.775-2」(Intornational Telecommunication Union 2006年)
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.775-2-200607-I!!PDF-E.pdf
「5.1chサラウンド番組の制作技術ガイドライン」(電波産業会 2010年)
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B30v1_0.pdf
「マルチチャンネルオーディオ用スピーカーセッティングガイド」(パイオニア 2002年)
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=1023
しかし、「ステレオ再生」に関する良い資料はなかなか見つかりません。。。
ようやく見つけたのが、
ダイヤトーンで2S-305やDS10000など、1000機種以上のスピーカー開発に携わった
佐伯多門氏の著書「スピーカー&エンクロージャー百科(誠文堂新光社)」の中にに『ステレオ再生の望ましい配置』として紹介されていた図を見つけました!!
それがコレ。

<クリックで拡大>
この図をスピーカーカタログに載せたら、売り上げ減少間違い無しですwww