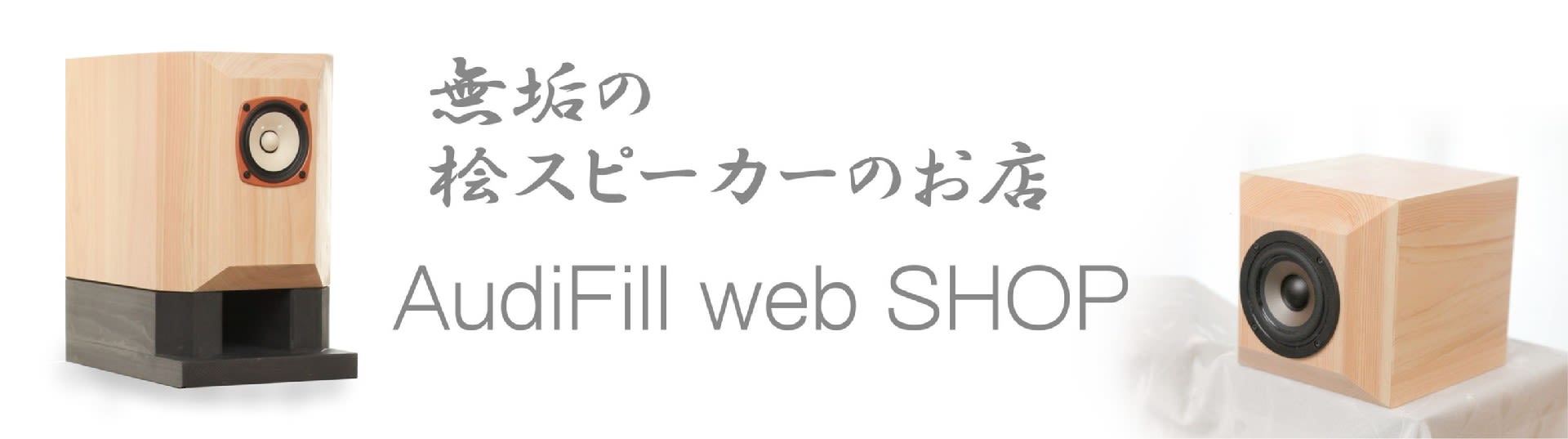今日は、「高音」についてお話しようと思います。
高音といっても様々ですので、今日はシャンシャンと鳴る7~15kHz付近の所にフォーカスしてお話しします。
高音は、低音と同じく、バランスが大切です。例えば、低音が少なく高音ばかりが目立っていると「ハイ上がり」と呼ばれますね。
スピーカー開発では「周波数特性」として、ほぼ全てのスピーカーで測定し管理しています。
少し昔のスピーカーであれば、ツイーターやミッドレンジにアッテネーターが付いており、ユーザーが自由に中高音の音圧を変え、全体バランスを調整することができました。
もう少し深い話をすると、高音は音圧だけでは割り切れない要素が多々あると感じています。
周波数特性がフラットでも、設計次第で、スッキリと伸びた高音にしたり、丸っこく穏やかな高音にすることもできます。
その因子の一つに、素材の音、というのがあります。
木材が固有の響きを持っているのは良く知られていますが、全ての素材が固有の音を持っています。
例えば、同じ金属でも、真鍮は穏やかにロールオフする高音、アルミはスッキリと伸びた高音、という個性があります。
こうした違いが周波数特性に現れることは少ないのですが、意識して使い分けることで高音の雰囲気を変えることができるのです。
他にも、スピーカー内部にある吸音材の使い方も、大きな影響があります。
スピーカー内部に反響した音は、かならず外に漏れ出てくるので、内部の吸音材でどう処理をするかで音が大きく変わってきます。
面白いことに、高音を吸いやすいと言われる吸音材を増やしても、必ずしも高音が減る結果にならないのです。
吸音材により中音の付帯音が減り、その結果で高域がクッキリと浮かび上がるということも十分にありますね。
同じように、スピーカーの箱鳴りも、高音表現に大きな影響があります。
箱の強度が不足し、ボンボンと中低域ばかりが膨らんでしまう昔の安いスピーカーをイメージすると分かりやすいかもしれません。
箱鳴りは決して悪ではありませんが、コントロール出来ていないと良い結果には至りません。
精緻でスピード感に溢れる高音を狙うのであれば、しっかりとした箱強度を狙いたいところです。
逆に、倍音豊かで柔らかい高音を狙う場合は、良質な木材を用いて適度な箱鳴りを促すのも好ましい選択です。
スピーカー設計の立場でお話してきましたが、完成品スピーカーであってもインシュレーターや、部屋の響きを整えることで大きく高音の印象を変えることができます。
求める音のイメージがついたら、様々な角度からアプローチして、自分ならではの音を作っていく。 高音に限らず、こうした取り組みはオーディオの楽しみの一つだと言えるでしょう。
![]()
![]()
![]()
高音といっても様々ですので、今日はシャンシャンと鳴る7~15kHz付近の所にフォーカスしてお話しします。
高音は、低音と同じく、バランスが大切です。例えば、低音が少なく高音ばかりが目立っていると「ハイ上がり」と呼ばれますね。
スピーカー開発では「周波数特性」として、ほぼ全てのスピーカーで測定し管理しています。
少し昔のスピーカーであれば、ツイーターやミッドレンジにアッテネーターが付いており、ユーザーが自由に中高音の音圧を変え、全体バランスを調整することができました。
もう少し深い話をすると、高音は音圧だけでは割り切れない要素が多々あると感じています。
周波数特性がフラットでも、設計次第で、スッキリと伸びた高音にしたり、丸っこく穏やかな高音にすることもできます。
その因子の一つに、素材の音、というのがあります。
木材が固有の響きを持っているのは良く知られていますが、全ての素材が固有の音を持っています。
例えば、同じ金属でも、真鍮は穏やかにロールオフする高音、アルミはスッキリと伸びた高音、という個性があります。
こうした違いが周波数特性に現れることは少ないのですが、意識して使い分けることで高音の雰囲気を変えることができるのです。
他にも、スピーカー内部にある吸音材の使い方も、大きな影響があります。
スピーカー内部に反響した音は、かならず外に漏れ出てくるので、内部の吸音材でどう処理をするかで音が大きく変わってきます。
面白いことに、高音を吸いやすいと言われる吸音材を増やしても、必ずしも高音が減る結果にならないのです。
吸音材により中音の付帯音が減り、その結果で高域がクッキリと浮かび上がるということも十分にありますね。
同じように、スピーカーの箱鳴りも、高音表現に大きな影響があります。
箱の強度が不足し、ボンボンと中低域ばかりが膨らんでしまう昔の安いスピーカーをイメージすると分かりやすいかもしれません。
箱鳴りは決して悪ではありませんが、コントロール出来ていないと良い結果には至りません。
精緻でスピード感に溢れる高音を狙うのであれば、しっかりとした箱強度を狙いたいところです。
逆に、倍音豊かで柔らかい高音を狙う場合は、良質な木材を用いて適度な箱鳴りを促すのも好ましい選択です。
スピーカー設計の立場でお話してきましたが、完成品スピーカーであってもインシュレーターや、部屋の響きを整えることで大きく高音の印象を変えることができます。
求める音のイメージがついたら、様々な角度からアプローチして、自分ならではの音を作っていく。 高音に限らず、こうした取り組みはオーディオの楽しみの一つだと言えるでしょう。